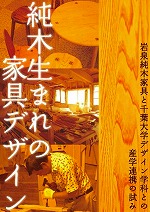|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
|
【縄文民族】 岩泉町の隣村 田野畑村にも アイヌについて興味深い話がある。 田野畑村 島越の人たちが北海道旅行に行ったとき「田野畑から来たんだって?」とアイヌの一人が寄ってきた。「家のお祖父さんが亡くなるとき『何か言い残すことはないか?』と尋ねたら『田野畑のハイペの垂水(たるみず)の鮑(アワビ)を食いたい』と言って亡くなった」という。 そのお祖父さんも子供時代に田野畑村で暮らしていて、北海道に移ったんだ と思われる。 東北の地名には、アイヌ語がたくさん残っている。岩泉の象徴的な山“宇麗羅”うれ〜ら と呼ぶ。夏に霧にすっぽりと包まれて姿が見えない日がある。配羅(はいら)、高須賀(たかすか)、赤須賀(あかすか)、尻高(しったが)、女辺(おなッぺ)、等々、ヤマト言葉では、意味が理解できない地名がいっぱいある。 |
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|
|
||
|